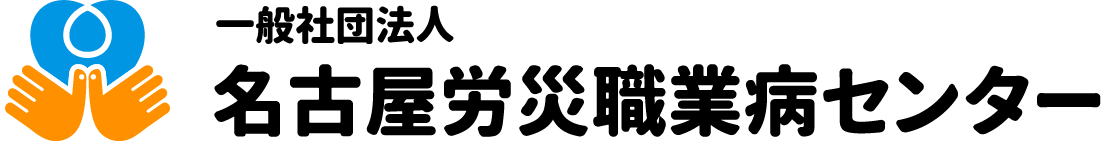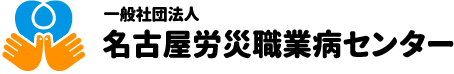News / お知らせ
大量発汗を伴う作業に従事し脳梗塞を発症したブラジル人労働者の労災認定/発症1年9か月後に半田労働基準監督署が業務上の判断(2022年6月)
2025.06.11|相談事例
2020年7月9日、ブラジル出身のTさん(62歳)は、夕方5時に起床し、コーヒー、サラダ、ヨーグルト、バナナなどの食事を取った後、妻の作ってくれた弁当を持って午後6時40分に自宅を出て、自家用車で就業場所の工場に向かいました。工場に到着した後、Tさんは、クーラーの効いた休憩室で休憩していました。あまり遅く職場に着くと、駐車場が一杯になることから、Tさんはいつも早めに自宅を出ていました。休憩室からTさんの作業場所までは徒歩で10分から15分かかりました。12時の休憩は1時間ありますが、10時と3時の休憩は10分間なので、トイレや汗で濡れた下着の着替えを済ませるだけでした。生産が忙しいときは、他の労働者と交代で10分間のトイレ休憩を取っていました。
Tさんは、愛知県東海市の派遣会社から同市内の高吸水樹脂製造工場に派遣され、紙おむつや生理用ナプキンの吸収材として使用されている高吸水樹脂(高吸水性高分子)をフレコンバックに詰める作業に従事していました。高吸水樹脂は、特に高い水分保持性能を有するように設計された高分子素材です。Tさんのこの工場での勤続年数は23年になっていました。7月9日は、午後8時の始業とともに作業を始め、800kgのフレコンバックへ粉末状素材を投入した後、フレコンバックの投入口をひもで縛り、フレコンバック全体をラップする作業を行いました。フレコンバック投入口をひもで縛る作業は、後でほどく時にほどけやすいように縛る必要がありました。フレコンバックは800kg入りと1トン入りの2種類がありましたが、この日は800kgのフレコンバックの作業だけでした。
800kgのフレコンバックの作業は、最初にTさんがフレコンバックの吊りベルトを、機械の樹脂投入部の下に4か所あるフックに架けて設置します。その後、ボタンを押すと粉末状素材の投入が始まります。投入量などは作業開始前に機械に設定をしておきます。投入が終わるとフックに架けられたフレコンバックが自動で上下に振られ、フレコンバック内部の粉体がゆすられフレコン内で均一に収まるようにされます。その後、自動で下におろされ、ボタンを押すとひもを結んだり、ラップしたりする場所までフレコンバックが自動で移動されます。粉体が投入された800kgのフレコンの口のひもを縛り、ラップをする作業はTさん1人で行い、1時間に10個、この作業を行います。フレコンのひもを縛る時に、後で会社に提出するサンプルを取る作業も同時に行いました。
Tさんの作業時の服装は、長袖の作業着に普通のマスクをし、髪の毛が製品に入らないよう頭に白い帽子をかぶり、その上にヘルメットをかぶっていました。作業場に入る時は、靴を履き替えていました。
Tさんが仕事をしていた作業場は室温が高く設定してありました。Tさんによると30度くらいあったのではということでしたが、現場の室温が高くされていた理由は、工場で生産されていた紙おむつや生理用ナプキンの吸収材に使用される高吸水性高分子素材が、冷たくなると固まる性質があったことから、機械の樹脂投入部には、製品である粉末状素材が詰まらないよう、温かい空気がいつもあてられていたからでした。それだけでなく、粉末状の素材をフレコンバックに投入する作業場内の室温を高く保つため、外気が中に入らないよう、作業場入口はビニール製のシャッターで遮蔽されていましたので、熱が常に室内にこもっていました。
作業場の室温が高く、作業中に大量に汗をかくことと、粉末状素材がべたべたになりシャツに付くことから、Tさんはいつも複数枚の着替え用のシャツを持って作業場に入り、休憩時や作業途中に着替えていました。夏は4、5枚の着替え用のシャツを持ち、冬場は3枚の着替え用シャツを持って作業場に入っていました。冬場でもたくさん汗をかきました。作業途中でシャツを着替えるタイミングは、粉末状の素材がフレコンに投入される数分間の間でした。工場に出勤する時は、着替え用のシャツだけでなく、いつもスーパーのビニール袋を持って出勤し、汗でびしゃびしゃに濡れたシャツを入れて家に持ち帰っていました。シャツは妻が洗濯をしてくれていました。
Tさんはいつも職場に入る時に、容器に氷を入れた2リットルのお茶を持ち込んでいました。7月9日から10日にかけての夜勤時は、お茶は休憩室に置いてありました。仕事中にお茶を飲むことは、作業場に粉末状素材の粉じんが飛散し、ほこりが酷かったのでできませんでした。
7月9日の午前12時に休憩に入った時、Tさんはまず、汗で湿ったシャツを着替えました。気分が少し悪く、食欲がなく弁当をほとんど食べることが出来なかったことから、お茶だけ飲んで休憩をしました。
この夜は、10時と3時の休憩でも汗で湿ったシャツを着替えましたが、シャツは汗でびちゃびちゃに湿っていました。
12時の休憩が終わり、Tさんは、800kgフレコンバックの作業に戻りましたが、自身の足が上手く動かないことに気が付きました。800kgのフレコンバックの投入口のひもを縛ったり、ラップを巻いたりする作業時に使用する2段の階段を上がる時に、足が上がらなくなっていましたが、作業を続けていました。
午前7時頃、Tさんは、ロットごとの作業について記入し、サンプルとともに工場に提出をする用紙の記入をしようとしましたが、右手がうまく動かず、変な文字しか書けなくなっていました。用紙はTさんに代わり、日本人の同僚が記入を行いました。
仕事が終わり休憩室に行く時、Tさんはふらふらとびっこを引きながら歩きました。その姿を見た人からは、Tさんがまるでお酒を飲んで酔っ払って歩いているようだと言われました。日勤者の出勤を確認するために休憩室に来ていた、普段は事務所で仕事をしている現場リーダーが、Tさんに1人で帰ってはいけないと言ったことから、派遣会社の日本人男性に自宅まで送ってもらうことになりました。派遣会社の日本人男性は現場リーダーが事務所に電話をして呼びました。Tさんは自分の自動車を工場に置いたまま、派遣会社の男性の運転する自動車で自宅のある団地に戻りました。団地に着いた時、Tさんは、携帯電話で妻に連絡し、団地の1階まで健康保険証とかかりつけの内科クリニックの診察券を持ってくるよう頼みました。そのまま、派遣会社の男性の運転で内科クリニックに向かいました。内科クリニックまで送ってくれた派遣会社の男性は、会社から田Tさんを病院まで送っていくように言われているとTさんの妻に話していました。内科クリニックは、持病で以前より通院しており、薬を処方してもらっていました。
内科クリニックには午後12時半くらいまでいて、点滴を受けたりしました。内科クリニックの看護師さんが妻に、着替えをもってくるよう電話をしました。Tさんのズボンなどは汗でべたべたになっていました。妻が内科クリニックにTさんの着替えを持って迎えに行ったとき、Tさんはしっかり歩くことが出来ず、口が少し歪んでいたということでした。Tさんは、タクシーで帰宅しました。
自宅に戻り、休んだ後、職場に置いてある自動車を取りに行きたいと思いました。友人に自動車の置いてある工場の駐車場まで車に乗せていってもらうことを頼み、1階までエレベーターで降りていきましたが、ふらふらしてきちんと歩けなかったことから、同居する娘の肩につかまって歩き、1階まで行きました。
Tさんが1階まで降りていくと、友人の息子さんがTさんの異常に気付き「おじさん口が変だよ」と言いました。息子さんは、自身が選手として所属するフットサルクラブ、名古屋オーシャンズの医師に電話で問い合わせてくれました。名古屋オーシャンズの医師はすぐにTさんを病院に連れていくよう指示したということで、内科クリニックの医師に電話をしてどの病院にいくか相談しました。
午後6時に南生協病院に行き、頭部画像を撮影されましたが、検査のために必要な機械がないということで、南生協病院の救急車で藤田医科大学病院に行きました。この間は友人の息子さんが付き添ってくれました。
Tさんは藤田医科大学病院で脳梗塞の診断を受け、入院しました。入院の翌日、Tさんはしゃべることが出来ず、手も足も動かない状態になっていました。藤田医科大学には12日間入院しました。
Tさんの右上肢と右下肢には重篤な麻痺が残りました。藤田医科大学退院後、リハビリテーション病院に転院し3か月間入院しながら歩行訓練や装具療法等のリハビリに取り組みましたが、現在のTさんの状態は杖と妻の介助でようやく歩ける状態です。
働くことが困難になってしまったことから、昨年6月にTさんご夫妻は名古屋ふれあいユニオンから紹介され労職研に相談に来ました。筆者は、愛知県図書館で脳梗塞関係の書籍を調べたり、大量発汗を伴う深礎掘り作業に従事したことから脳梗塞を発症し、1989年に労災認定された55歳の男性深礎工のケースについての関西労働者安全センター機関紙記事等を読んだりして、脱水症状が脳梗塞の原因になることを知りました。脱水症状になると、血液中の水分が少なくなり、血液の濃度が濃くなって、血栓ができやすくなり、梗塞を起こす確率が高まるのです。筆者は、Tさんのケースも労災請求できるのはと考え、Tさんに請求を勧めました。労災請求に際して、派遣会社に労災保険請求書へ在籍の証明を求めましたが拒否されました。
昨年9月に半田労働基準監督署に労災請求したところ、今年4月8日付けで業務上災害と認定されました。脳梗塞を発症してから1年9か月が経過していました。
Tさんは、現在でも懸命にリハビリに励んでいます。