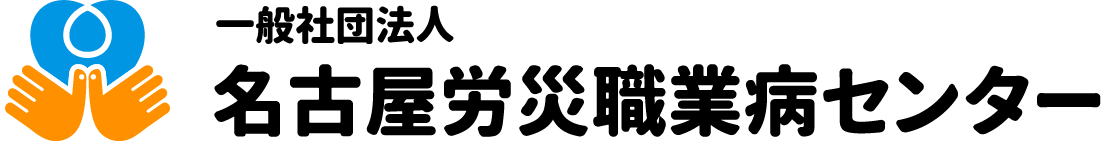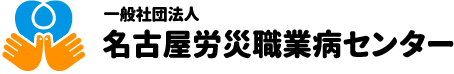News / お知らせ
適応障害で労災認定~新認定基準に基づき認定される~(2013年4月)
2024.04.24|相談事例
病気(抑うつ状態)になったのは仕事が原因とするKさんの労災請求をサポートしていた事案が、昨年10月、岡崎労働基準監督署より、労災認定されました。
Kさんは派遣会社だったT社の福岡営業所に派遣社員として入社しましたが、その後、正社員としてT社の東海事業部に赴任しました。
Kさんはそこで、営業管理職として、派遣スタッフの業務管理を行っていました。
具体的には派遣スタッフの送迎や厚生(寮の世話や寮費等の回収)等といった派遣スタッフの全般的な管理をする一方で、客先(派遣先の会社)のクレーム処理や客先の新規開拓等といった営業もしていました。
会社から派遣スタッフへの指示はKさんを介して行われ、また、客先からのクレームも初動の対応はKさんがしなければなりませんでした。
この様にKさんは会社と派遣スタッフ、会社と客先との間で、板挟みの状態で働いていました。
T社では営業管理の担当者は客先を3~5ヵ所程担当しており、当然、担当する客先が多ければ、担当する派遣スタッフの数も多くなります。
派遣スタッフの全般的な管理の中には派遣契約の打ち切りによる退職者の対応や派遣スタッフが事件を起こした際の警察対応等も含まれていました。
2010年の2月中旬頃、Kさんが担当していた元派遣スタッフが、リーマン・ショックの際の派遣切りを巡る対応を逆恨みし、T社の寮に放火するという事件が発生しました。
更にその約2週間後の2月下旬頃、今度は別の元派遣スタッフがT社の寮の一室でミイラ化し、全裸で死亡しているのを発見するという事件が発生しました。
因みにKさんはリーマン・ショック当時、会社の命令で、派遣切り対応をせざるを得ませんでした。
Kさんは退職者の為に助成金の申請や再就職等に関する助言もしていましたが、結果的に雇用を失った元派遣社員達のKさんに対する風当たりは厳しいものでした。
また、ミイラ化して死亡していた元派遣スタッフもリーマン・ショックの際に派遣切りされましたが、その後も会社の寮に住み続ける事を認められていました。
Kさんはこれらの事件の際の警察での事情聴取や捜査協力、葬儀の手配や遺族への対応や部屋の後片付け等を通常の業務もこなしながら行った為に長時間労働を強いられました。
Kさんは上司にも相談しましたが、会社の支援が一切得られなかった事で、遺体発見の約2週間後の3月中旬頃から、全裸の遺体が頭に浮かぶ様になり、不眠がちになりましたが、医療機関を受診する事はせず、市販の睡眠導入剤を服用する事で症状を押さえながら、勤務を続けました。
4月になると労働者派遣法における抵触日問題(※)への対応の為の業務請負化の準備が本格化し、仮想請負化が始まりました。
9月下旬からの正式な業務請負化のスタートへ向けて、請負単価の設定の為の生産量や労働時間数等のデータ収集を、これも通常業務と並行しながら行いました。
実際に業務請負業が始まった以降もT社は派遣業を継続しており、ここでもまた、それまでの通常業務に加え、請負管理業務も担当した事で、月に100時間を超える時間外労働が発生しました。
また、Kさんには請負業務の経験は初めての事で、慣れない中での業務も負担になりました。
ところが、翌2011年の1月、Kさんと一緒に請負管理業務に携わり、現場管理を担当していた同僚が担当業務を放置したまま、突然、失踪してしまいました。
そのしわ寄せがKさんを襲った事で、Kさんの業務量は増加し、過重労働が発生しました。
会社は、突然、失踪した同僚の補充として、2月中旬から、新入社員を雇い入れましたが、この新入社員の教育もKさんが行っており、とても会社によるKさんへの支援があったとは言えない状況であり、ここでも月100時間を超える時間外労働が発生しました。
その後、Kさんは体調に著しい変調を感じ、胸が押さえ付けられる様な苦しさを感じた事で、通勤途中にあったメンタルクリニックを受診し、抑うつ状態と診断され(開示請求して分かったところでは、診断名は抑うつ状態だけではなく、反復性うつ病障害ともされていました)、それ以降、会社を休業しました。
労災請求にあたっては、放火や死体発見のふたつの事件の後に体調に不調が表れた2010年の3月下旬が発症時期ではないかとして労災請求しましたが、労災認定にあたって岡崎労働基準監督署はKさんがメンタルクリニックを受診した2011年の2月下旬を発症時期としました。
また、疾病名も抑うつ状態ではなく、適応障害としました。
Kさんの労災認定は一昨年末に策定された新認定基準に基づき、判断がされています。
請求時の主張としては放火や死体発見というふたつの事件とその後の対応等により、病気を発症したのではないかとしましたが、労災認定にあたっては同僚の突然の失踪が直接的なきっかけであり、それに加え、その前後の恒常的な長時間労働と会社の支援がなかった事が相まって、適応障害を発症したとされました。
認定基準に沿って言えば、同僚の失踪時の状況を「仕事の内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」という出来事に当てはめ、これだけでは心理的負荷の総合評価は中にしかならないところを、その前後の恒常的な長時間労働をプラスして評価する事で、最終的な心理的負荷の総合評価を強と判断しています。
聞いたところでは新認定基準が策定されて以降、時間外労働に対する評価の仕方が大きく変わった事で、今回と同様の形(出来事+その前か後の恒常的な長時間労働=総合評価が強)で労災認定されているケースや審査請求で自労基署による取り消しになったケースが目立っているとの事でした。
Kさんの労災請求にあたっては旧判断指針に基づく主張をしましたが、一方で、新認定基準が策定される事も意識しながら、その内容がおおよそ明らかになったのを確認して、請求にあたりました。
今回、岡崎労働基準監督署が新認定基準に基づき認定した月100時間という時間外労働時間数は、旧判断指針で判断された場合、必ずしも恒常的な長時間労働と判断されるとは言い切れない数字であり、新認定基準の影響を大きく受けた労災認定だったと思います。
そういった事はともあれ、こういう活動をしているとそんな難しい問題に目を向けがちですが、労災請求をしても認められない人が多い中で、労災認定された事は何よりだったと思います。
(※)労働者派遣法では政令26業務以外の自由化業務について、派遣社員の受入期間に制限を設けています(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長が可能になる)。
抵触日とはこの期間の制限に抵触(違反)する事になる最初の日(派遣可能期間終了日の翌日)の事です。