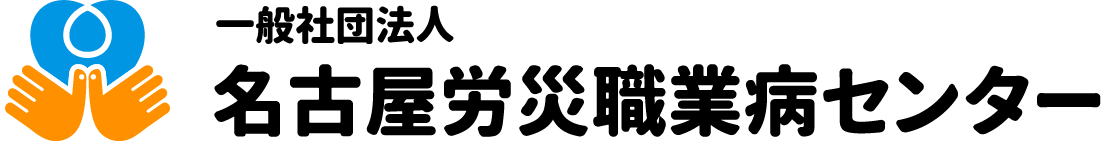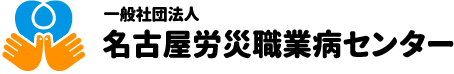News / お知らせ
長距離トラック運転手のAさん脳出血で業務上の認定(2011年7月)
2020.06.24|相談事例
1月下旬にAさんから、「(名古屋南労基署から、)労災認定との連絡があった。」と連絡を受けました。
Aさんは長距離トラックの運転手をされていましたが、昨年の2月3日の夕方頃、奈良県の運送先で、432袋の米袋の積み降ろし作業中に、小用の為、運送先の事務所のトイレに行ったところ、倒れ込み、救急隊により、そのまま近くの病院へ搬送、脳出血と診断され、手術入院する事になりました。
幸い一命はとりとめましたが、Aさんには重度の後遺症が残り、その後、愛知県内にある居住地の近くの病院に転院し、リハビリ加療を継続されてこられました。
その後も幾つかの病院を転院する事にはなりましたが、現在では、半身に麻痺が残る常態ではありますが、ゆっくりとなら自立歩行が可能で、ヘルパーさんの助けを借りながらではありますが、一定の生活が可能な状態にまで回復をされました。
センターがAさんの事案をサポートするきっかけは、Aさんのお兄さんからの相談でした。
Aさんのお兄さんは、ご自身もご病気を抱えながら、Aさんが倒れて以降、献身的なサポートを続けてみえましたが、Aさんの勤務先の運送会社の対応が酷く、病院のケースワーカーのみのサポートにも限界を感じ、行き詰った状態の時、知人からセンターを紹介されたそうです。
Aさんが勤務していた運送会社は、Aさんが倒れた際、労災申請を行いました。
これ自体は当然の行為ですが、その後、会社は、リハビリ加療中のAさんの病室を訪れ、退職手続きに同意させた上で、離職票を発行し、Aさんに傷病手当金の申請書を渡したのでした。
Aさんのお兄さんは、その申請書を持って奈良県の病院まで訪れ、手続きをしようとしたら、「これは労災の時の書類ではありませんよ。」と言われたそうですが、至極もっともな話です。
しかも後に判明したところでは、この時のAさんは、傷病手当金の受給要件を満たしていませんでした。
そんな状態の中で、Aさんは、当事入院していた病院から、医療費や入院等の費用の請求をされていたのでした。
労災申請してあるのにもかかわらず、何故、費用の請求をされるのかを確認したところ、その病院が労災指定病院であるにもかかわらず、転院の手続きをした人は誰もいませんでした。
会社も転院の手続きをしていなければ、病院も労災申請中のケースである事を認識していながら、転院の手続きをする事はなく、またAさんのお兄さんも労災申請に対する知識がありませんでした。
その後、6号様式を病院に提出し、転院の手続きを行いましたが、それでも病院は、AさんとAさんの親族に対して、労災が不支給になった時は、医療費や入院等の費用を支払う事の誓約書にサインする事を求めました。
何故そこまでするのかの説明を求めたところ、病院側の回答はこうでした。
「医療費の未収が発生すると、自分達の賞与が減額される。病院や自分達にとって死活問題だ。」
現在、医療費の未収が社会的な問題になっていますが、その負の連鎖が、こんなところにも影を落としていました。
その後、Aさんの発症時の同僚の方達に病院の近辺まで来てもらい、Aさんが倒れられた当時の仕事の内容や会社の事についての聴き取り調査に協力してもらいました。
また、ユニオンから運送業界に関する助言を得たり、ひょうご労働安全衛生センターから、拘束時間に関する資料を得たりもしました。
そして、それらを基に、労基署と折衝し、その結果(なのかどうかは分かりませんが)、冒頭で紹介した結果となりました。
ここからは開示請求した復命書から明らかになった認定理由についてみていきます。
労基署による総合判断は、過重負荷について、「異常な出来事」や「短期間の過重業務」には該当しないが、「長期間の過重業務」については、労働時間は、発症前1ヵ月間の時間外労働時間数が110時間15分であるから、業務と発症の関連性は強く、また勤務に不規則性があり、拘束時間の長い勤務である事から、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるので、Aさんの脳出血の発症は業務上であるとのものでした。
これだけを読むとそうなのかで終わってしまいそうですが、資料を読み進めていくと拘束時間をどう判断するかという問題に突き当たります。
冒頭で記した通り、Aさんは長距離トラックの運転手をしていました。
長距離トラックの運転手というと、大抵の方が、長時間労働の過酷な業務というイメージを浮かべると思いますが、少なくても労災保険の運用上においては、単純にその拘束時間が長い=長時間労働とは認められないのが現状です。
労基署が認めたAさんの発症前1ヵ月間の時間外労働時間が110時間15分である事は前述しましたが、労基署が認めた発症前1ヵ月間の拘束時間は、471時間30分です(因みに、その前の一ヵ月間は、拘束時間が409時間15分、時間外労働時間は、139時間40分)。
拘束時間471時間30分の内訳は、所定内労働時間が286時間15分で、時間外労働時間が110時間15分で、休憩時間が185時間15分と判断されています。
しかし、Aさんの場合、「短期間の過重業務」については、発症前7日間の内、
①午前0時を跨ぐ日が4日間あり、
②全日において始業時刻は一定でなく、
③1日に16時間以上拘束されている日が4日間あり、
④休日も一日もなく、
⑤拘束時間は130時間だったにもかかわらず、
⑥認められた時間外労働は、27時間15分でしかなく、
⑦総合評価としては、特に過重な業務に就労したとは認められない
と判断されています。
つまり、1ヵ月間でみると過重な業務に就労したと認められるが、それを4分の1単位(=1週間)でみると過重な業務に就労したと認められないと判断されている訳です。
読んでいて何かおかしいと感じませんか?
何故この様な問題が発生するのかといえば、休憩時間を巡る問題が発生するからです。
これが一般的な働き方をしており、何の問題もない場合であれば、休憩時間を労働時間とする事はできませんが、長距離トラックの運転手という様な特殊な働き方の場合に、Aさんの様に何百時間も拘束されていれば、拘束時間=長時間労働としての加重性を判断して、業務上として扱うべきではないでしょうか。
先頃、厚生労働省より、平成22年度における脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況のまとめが公表されましたが、この中で、業種でいえば、運輸業・郵便業の中の道路貨物運送業、職種でいえば、輸送・機械運転従事者の中の自動車運転従事者の脳・心臓疾患における労災認定件数は、飛び抜けています。
「長期間の過重業務」ないし全体をみた場合については、拘束時間に関する運用がある様ですが、「短期間の過重業務」を判断する段階で、拘束時間=長時間労働であるという様に拘束時間に対する加重性の判断や運用のあり方が変っていかなければ、その数字は減らないのではないかと思わせるAさんのケースでした。