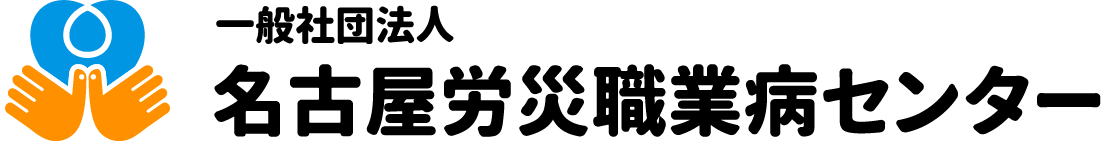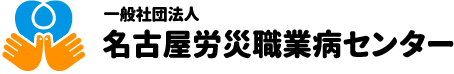News / お知らせ
被災者死亡後のアスベスト関連疾患の労災認定~悪性胸膜中皮腫と石綿肺の2つの認定事例から~(2011年9月)
2020.06.24|相談事例
最近、アスベスト関連疾患ですでに亡くなったお二人の方々の労災認定が認められました。一人は1996年に悪性胸膜中皮腫で亡くなった製鉄会社に勤めていた男性の事例で、もう一人は2009年に石綿肺で亡くなった鉄工所に勤めていた男性の事例でした。二つのケースに共通していたのは、悪性胸膜中皮腫で亡くなった男性の死因が「出血性胃潰瘍」で、石綿肺で亡くなった男性の死因が「腹部大動脈瘤破裂」で一見、直接死因がアスベスト関連疾患とは因果関係が無いように見え、特別遺族年金と遺族補償給付の支給対象になるか危ぶまれる事例であったことです。実際、石綿肺で亡くなった男性のケースは、三島労働基準監督署で遺族補償給付の不支給決定を受けており、その後の静岡労働局での審査請求でも訴えを棄却され、今回、再審査請求での原処分取消しでした。
1.直接死因が出血性胃潰瘍の中皮腫の被災者の事例
愛知県内に住むR婦人から相談電話を最初にいただいたのは2009年の12月でした。相談内容は、「1996年の3月に夫が中皮腫でなくなったのですが、アスベストが原因ではないですか?」というもので、療養中は傷病手当金の支給を受けており、労災申請は行っていないということでした。早速、R婦人、被災者の娘さんと直接面談を行い職歴や受診、手術、入院歴などの聞き取りを行いました。この時の聞き取りで分かったことは、被災者が1993年6月に名古屋市立大学病院で左肺全摘手術を受けたこと。30年以上、大手製鉄会社の工場に勤務されたこと。亡くなったのは1996年3月25日に名古屋市立大学病院で、たまたま口腔外科を受診中に気分が悪くなり倒れ、検査を受けた結果、消化管の出血が認められ、手術で止血を試みている最中に死亡したことでした。また、労災、石綿救済法共に申請したことはありませんでした。面談で製鉄関係の仕事では工場設備の断熱材に石綿製品が使われていた可能性があること。労働者も作業中に石綿布などを使用していた可能性があること。製鉄業界ではアスベスト労災認定が比較的多いことなどを伝え、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が既に消滅していても、石綿による健康被害の救済に関する法律の改正により、特別遺族年金の申請が可能であることを伝えました。R婦人と娘さんは特別遺族年金を申請することを決め、筆者は申請に向けての支援を開始しました。
申請に当たってまず、名市大病院にカルテ開示請求を行いました。開示請求前に名市大のソーシャルワーカーと打ち合わせを行いましたが、カルテ、画像の保存期限は5年間で残っているかどうかは分からないということでした。カルテ原本、画像は保存されていませんでしたが、幸いカルテを複写したマイクロフィルムがあり、当時のカルテを入手することが出来ました。カルテで被災者が悪性胸膜中皮腫であったことが分かりましたが、問題は死亡診断書の直接死因が「出血性胃潰瘍」であったことでした。R婦人によると、被災者は左胸膜肺全摘手術後、左横隔膜ヘルニアをきたしたということで、死因は中皮腫と因果関係がありそうでした。早速、杉浦、森両医師に相談し、杉浦医師から、中皮腫は致死的な病気で、患者さんも相当のストレスを抱えるので十二指腸潰瘍による出血死などは相当因果関係があると言われているし、当時の主治医に左横隔膜ヘルニアと出血性胃潰瘍の関係を証明してもらえば認定は取れるだろうというアドバイスをもらいました。実際、カルテには左横隔膜ヘルニアにより胃の位置が上昇したことが記入されていました。被災者の死亡診断書を記入した医師が名古屋市内で開業しているのを突き止め、R婦人、娘さん、筆者と訪問し当時の医師に意見書作成の協力を要請しました。医師は快く引き受けてくださり、中皮腫の手術後、左横隔膜ヘルニアをきたし、胃潰瘍が下行大動脈に突破し大量出血により死亡という意見書を作成してくれました。手術後、胃の位置が上昇していたのに加え、胃潰瘍によって胃の内側が削れ、胃の突起した部分が肺近くを通る下行大動脈にかかり、突起した部分が破裂した時に下行大動脈も破れ、大出血を起こし死に至ったという内容です。被災者の主治医と弊センターの森医師はお互い面識があり、弊センターからの参考資料の提供などが円滑に進んだのは幸運でした。
特別遺族年金支給請求書の会社証明欄に被災者の石綿ばく露作業の従事期間と仕事内容を証明してもらう必要があり、筆者が製鉄会社に電話連絡を取りました。総務部の担当者は慣れている感じで書類を送ってくださいと簡単に筆者に伝えました。製鉄会社から返送されてきた請求書には被災者が1964年より製板、熱延工場で従事したこと。石綿製品が使用されている製鉄所の設備の整備をしたこと。特に保全作業時、ガス・アーク溶接の際、石綿製品を遮熱材として使用したことが記入されていました。
その後、2010年3月30日に参考資料、カルテなど共に特別遺族年金を名古屋南労働基準監督署に申請し、2011年2月23日に特別遺族年金支給決定となりました。製鉄会社は職場にアスベストが存在したことを認めており、中皮腫と合併症、直接死因との因果関係についての調査に相当の時間が費やされました。
2.直接死因が腹部大動脈瘤破裂の石綿肺被災者の事例
静岡県のY婦人から石綿肺で亡くなった旦那さんについての相談電話をいただいたのは、2010年の11月でした。「2005年9月から石綿肺で労災認定を受けていた夫が、2009年9月に腹部大動脈瘤破裂で亡くなった時に、遺族補償年金と葬祭料の請求手続きを三島労働基準監督署に行ったが、直接死因が石綿肺と因果関係がないとされ不支給になり、労働局に審査請求を行ったが2010年10月に棄却されてしまったがどうしたらよいか?年金だけでは生活も大変」というのが相談の内容でした。Y婦人には再審査請求書を労働保険審査会に取り急ぎ送るよう促し、証拠は追って提出すればよいと伝えました。Y婦人はすぐに再審査請求の手続きをとり、筆者も支援を開始しました。
最初にY婦人から静岡労働局での審査請求の決定書を取り寄せ、被災者の死亡状況が把握できました。被災者は1953から16年間、父親が経営する鉄工所に勤務し、石綿吹きつけ作業も行われていた建設現場で手すりやシャッターなどの金物取り付け工事を行い、多くの石綿含有建材を加工し石綿にばく露し、石綿粉じんを吸い込むことによりじん肺の一種である石綿肺に罹患しました。2005年にじん肺管理区分4の決定を受け、労災認定され療養中の2009年3月に腹部大動脈瘤が発見されましたが、石綿肺により酸素ボンベがなければ呼吸できない状態で全身麻酔をすることが不可能で手術が出来ず、その年の9月14日に腹部大動脈瘤が破裂し、緊急手術中に亡くなりました。決定書は遺族補償給付の不支給決定理由を「死亡以前に腹部大動脈瘤が発見されていたものの、石綿肺の著しい肺機能低下が原因として外科的手術を行えず破裂死亡に至ったものであるとしても、石綿肺と腹部動脈瘤の発症とは因果関係がなく、石綿肺と腹部大動脈瘤破裂による死亡との間に相当因果関係は認められない」としていました。しかしこの事例の場合、石綿肺による著しい肺機能低下のため腹部大動脈瘤の待機手術ができなかったのは明らかで、石綿肺が生じなければ、慢性呼吸不全も発症せず、手術による治療が出来るので腹部大動脈瘤破裂は発症しなかったと考えられ、この考え方だと石綿肺と腹部大動脈瘤破裂による死亡は相当因果関係があることになります。こういった考え方でこの事例に取り組むことを杉浦、森両医師と相談し、意見書の作成を森医師が行ってくれることになりました。
労働保険審査会への意見書の提出の方法は工夫しました。森医師の意見書を審査会へ送ることも有益であると考えましたが、やはり主治医であった方の意見書のほうが説得力があると考え、まず森医師に、「石綿肺がなければ、慢性呼吸不全とならず、腹部大動脈瘤があったとしても、手術ができるので破裂して死亡することは避けられた」旨のことを主治医の意見書に盛り込んでほしいという意見書のようなお手紙を作成してもらい、そのお手紙を主治医に送り、そのお手紙の内容を入れた正式な意見書を主治医に作成してもらうことにしました。被災者の主治医は快く意見書の作成をしてくださいました。また、森先生の手紙を送るときに「腹部大動脈瘤破裂に対する緊急手術成績」という国立循環器病センター心臓血管外科による論文を添付し意見書と共に労働保険審査会へ送ってもらうことにしました。論文の内容は、腹部大動脈瘤の待機手術による死亡率は1%以下に現在はなっているが、緊急手術の成績は以前として不良であるという内容でした。
2011年8月1日に労働保険審査会は、三島労働基準監督署の遺族補償給付と葬祭料を支給しない旨の各処分を取り消す裁決を行いました。裁決書は腹部大動脈瘤に対する手術成績を考慮して、石綿肺と腹部大動脈瘤による死亡との因果関係は相当あると判断しており、石綿肺があるために待機的手術が不能と判断され、腹部大動脈瘤破裂の恐怖に怯えながら半年余りの日々を過ごし、結果的に腹部大動脈瘤で亡くなった被災者の無念を考えると労災保険法の精神に則り、遺族補償給付と葬祭料を支給しない旨の処分の取り消しを望むというものでした。
まとめ
今回紹介した2つの事例では、死亡した被災者に関わっていた医師達が協力してくれたことが、認定を勝ち取るために重要な要素であったことは間違いありません。被災者に生前、直接関わった主治医の意見は説得力があり、労基署や労働保険審査会も重要な情報として採用する可能性が高まるからです。また労災申請にあたって、一見、アスベスト関連疾患とは関係ない死因でも、アスベスト関連疾患発症後に様々な合併症を発症する可能性があること。アスベスト関連疾患を発症した患者が受ける慢性呼吸不全の為に手術ができないというような医療実践上の不利益にも目を向ける必要があり、相談をを受けた支援者は、協力医等から常に的確な医学的アドバイスを受けることが重要であると思いました。的確なアドバイスがある場合、情報不足、病気に対する偏見や無知から解放され、支援者もその後の申請に向けての作業をかなり明確に組み立てることができ、効率的に活動することが可能になり支援を労災認定に結び付けやすくなるからです。今回の2事例の認定を勝ち取るのに、フレンドリーな杉浦、森両医師の存在は大きかったと考えています。