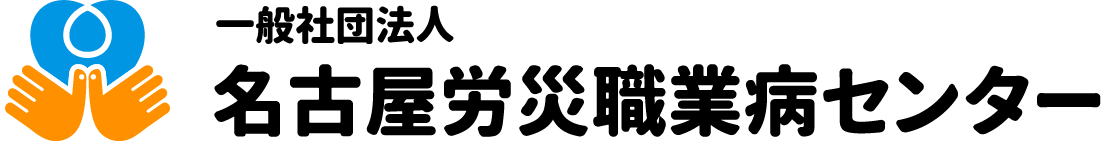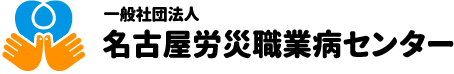News / お知らせ
労働保険審査会がタイル工のじん肺労災不支給決定取り消しの裁決(2017年5月)
2024.04.27|相談事例
今年2月10日、労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関である労働保険審査会がじん肺の増悪で亡くなったKさんの労災を認めない名古屋西労働基準監督署の決定を取り消す裁決をしました。
Kさんはタイル工として1955(昭和30)年2月から2002(平成14)年9月まで名古屋市内に本社を置くタイル工事会社に勤務し、ベビーサンダーを用いたタイル加工作業やタイル貼り作業に従事し、タイルをベビーサンダーで削る時に発生する粉じんや、コンクリートをかくはん機に投入する時等に粉じんにばく露しました。生前、じん肺管理区分決定は受けていませんでした。
Kさんは2010年に地元の総合病院を受診した際にじん肺症の診断を受け、通院・療養していましたが、2014(平成26)年4月3日、じん肺が悪化し呼吸不全で亡くなりました。息子のYさんは、父親の最後の姿を「口をすぼめて息をして本当に苦しそうで、かわいそうでした」と証言しています。
Kさんの死後、Yさんは2014年6月に弊センターに相談され、主治医に「じん肺による続発性気管支炎の急性増悪により死亡した」という内容の意見書を書いてもらい、2010年からじん肺とそれに続発する気管支炎に関する記録のあるカルテ及び痰の通院、入院時の微生物検査報告書等を添付し2014年7月に名古屋西労働基準監督署に休業補償給付及び遺族補償給付、葬祭料の請求を行いましたが、翌年2月にKさんの労災を認めない決定が下されました。理由は、「管理2相当のじん肺所見は認めますが、じん肺の合併症は認めない」というものでした。じん肺の労災は、じん肺管理区分が管理4か管理区分2又は3で続発性気管支炎、続発性気管支拡張症等の合併症が認められなければ労災認定されません。
筆者とYさんは憤りを憶えつつ2015年4月、愛知労働局に審査請求しましたが同年12月に棄却され、その後、労働保険審査会に再審査請求を行いました。
再審査請求で棄却されると後は行政訴訟を提起するしか方法が無くなるため、筆者とYさんは細心の注意を払い、造船労働者等多くのじん肺患者の治療に当たってきた横須賀中央診療所院長の春田明郎医師に意見を求めました。春田先生はKさんの2011年から2014年までの胸部画像を丁寧に読影して下さり、右上肺のじん肺による気腫性変化から発生した肺嚢胞(ブラ)が感染により徐々に悪化し、最終的に感染症により胸腔内に膿性(のうせい)の液体がたまる症状、膿胸(のうきょう)を肺嚢胞に発症した経過を確認して下さった上で、「(Kさんには)じん肺が存在し、肺嚢胞への感染により急性呼吸不全に至ったと推測いたします。肺嚢胞が続発性気胸と同じくじん肺に関連したものであれば、肺嚢胞に感染し療養し、死亡した場合も、続発性気胸と同等に、じん肺の続発性により死亡したと考えられます」という内容の意見書を作成して下さいました。筆者とYさんは春田先生の意見書を労働保険審査会に提出するとともに、労働保険審査会の審理の場においても「被災者は肺嚢胞への感染により急性呼吸不全に至り死亡しました」と主張しました。この頃、Yさんは東京転勤になっていたので、Yさんは東京の労働保険審査会で審理に出席し、筆者は愛知労働局からのテレビ審理に出席しました。
今年2月10日、労働保険審査会は2010年撮影のX線写真からKさんのじん肺が管理2相当であることが認められ尚且つ、2012年のCT画像により肺の両側にブラを含む気腫性嚢胞(きしゅせいのうほう)が多数見られ、気管支拡張もあり続発性気管支拡張症を確認することと肺両側に強い石灰化を伴った胸膜肥厚(プラーク)の確認が出来る上、2013年7月のCTより右上肺の巨大空洞内に液体貯留をきたし、感染性肺嚢胞の所見がある上、続発性気管支炎の存在が確認出来、さらに同年12月のCTでは感染症を引き起こす肺炎桿菌と両側の肺の間質影と線維化の進行が確認出来ることからタイル切断やセメント加工時の粉じん吸入により、肺気腫、肺の線維化を生じ、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症を合併し、その後、肺の線維化が進行し、胸膜肥厚などが混合した上に、感染症も加わり、呼吸不全で最終的に死亡したと結論付けました。
今回、Kさんの労災を認定させるのに大変苦労しましたが、原因は労働基準監督署の調査において、続発性気管支炎の認定基準、「おおむね3ミリリットル以上の膿性痰の2回採取」がカルテ、検査結果等で確認出来なかったということだけで、その後、画像による続発性気管支拡張症の確認を適切に行わず(そもそも見ていない)、画像及びカルテ及び検査結果に残された感染症についての正確な評価を行わなかったことでした。
昨年、大手タイルメーカーの工場でタイルを窯で焼く作業(焼成)に従事していた70代の退職者のじん肺合併肺がんの労災申請の支援をしたり、今年に入っても大手タイルメーカーの下請け企業で働く50代の労働者から「最近のじん肺健康診断でじん肺管理区分管理2の決定を労働局から受けたのでどうしたらよいか?」という相談を受けたり、同じく大手タイルメーカーの下請け企業で、10代の頃から成形の仕事に従事した労働者から、「30代で辞める時はじん肺管理区分管理3の決定を労働局から受けていたけれど、70代になりじん肺の合併症に罹り症状が悪化しています。労災申請は可能でしょうか?」という相談を受けたりして、タイル製造業で働いた労働者の中に救済されていない人々も相当いるのではと考えるようになりました。筆者の父親は大手タイルメーカーでエンジニアとして勤務していた経験があり、そのことから昨年のじん肺合併肺がんを患った大手タイルメーカーの元従業員のケースでは、父親にタイル工場内の焼成工程における粉じんばく露に関する意見書を書いてもらいました。幸いこの男性のケースが労災認定されて二人で喜びあったりしたのですが、父の思い出話で特に印象に残ったのは、工学部を卒業して配属されたばかりの頃、防じんマスクをしていた父に対し工場のたたき上げの労働者が「俺は工場内にチラチラ舞っている粉じんがかわいくて仕方がないよ」と父を揶揄するように言ったエピソードでした。当時の粉じん対策や労働安全衛生に対する意識がよく伝わってきました。